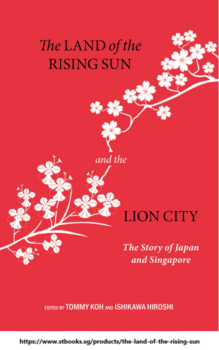サッカー少年、サッカーを仕事にする
M: こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。まず最初に何故サッカー関係のお仕事をすることになったのかお話しいただけますか?
K: 小学校の低学年からずっとサッカーファンでした。サッカー雑誌を買ってボロボロになるまで読んでいたおかげで、例えば小学校の授業中に、イタリアの都市名を20個も30個も言えてしまったんです。 周りはちょっとおかしいように思ったでしょうが(笑)、この時、サッカーと世界は繋がっているんだな、と感じました。
自分自身で人生をデザインするためには差別化が必要だと思い、大学は日本大学芸術学部演劇学科演技コースに進学しました。卒業する時がちょうど2002年日韓共催ワールドカップの年でした。初めて日本で開催されるワールドカップ、そして自分が生きている間では最初で最後かもしれない。一般の企業に勤めて事務処理をしている場合じゃない、サッカーの仕事をしなきゃ、と思いました。インターネットでサッカーの仕事を探していたら、”超ワールドサッカー“というモバイルサイトでアルバイトを募集していました。大学生の時には寝る間を惜しんでサッカーの記事を個人ブログで書いていたので、時給800円でしたが、好きなことができるなら、と応募しました。ところが、募集は1週間前に締め切られていました。でも、諦めずに電話をして、面接だけでも、とお願いして面接をさせていただいたら、合格をいただきました。200人中2人!確率100分の1!
M: すごいですね!
K: そしてもう一つ、横浜FCのオフィシャルライターという仕事にも応募しました。これも200人の応募者の中の2人に選ばれました!100分の1かける100分の1って、一万分の一じゃないですか。そうか、自分はこのサッカー業界で選ばれた人間なんだ、と大いに勘違いをしました(笑) 。でも、若者の勘違いはアクセルになるのですごくいい、 とは思っています。
そうこうしているうちに、モバイルサイトの会社で評価が上がってきてしまいました(笑)。大学生の時に趣味でやっていたことと同じこと、ただサッカーの記事をたくさん書いただけなのに、お金は稼げるし、褒められるし、時給は上がる。半年後には正社員にもなり、1年後には編集長になっていました。 “超ワールドサッカー”はワールドカップの時は15,000人ほどの会員数でしたが、その後15万人ぐらいまで増えました。
M: トントン拍子ですね。
K: 取材と称して 年の3分の1はヨーロッパにいて、ビールを飲んで、サッカーの試合を見て、原稿を書いて。この繰り返しです。これはいい仕事だなあ、と思っていました(笑)。その後、ヨーロッパでの仕事を積極的に作りました。FCバルセロナやマンチェスターユナイテッドのオフィシャルモバイルサイトを立ち上げたら、リバプールからは逆にうちもやりたいと話が来ました(笑)。マンチェスターには翌日くらいに飛んで打ち合わせをしました。
M: すごいですね!そこからどうやってアルビレックス新潟に繋がるんですか?
K: それからCDを出したり、 雑誌を出したり、マーチャンダイジングをやったり、広告のことをやったり。 サッカービジネスに関しては大体やらせてもらっているな、と思っていたところ、アルビレックス新潟シンガポールというチームの社長を探しているという話を聞いたので、手を上げました。サッカークラブの社長という仕事は、ドリームジョブだと思っていました。60歳ぐらいにできればいいなと思っていましたが、29歳で始めることになりました。