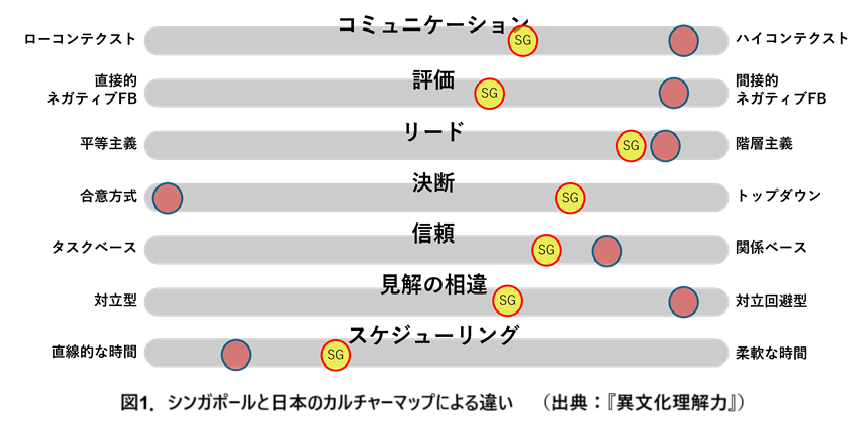オープンイノベーションが活況です。大企業から新しい事業を生み出すには、「スタートアップと組まなければならぬ」といった強硬派から、「スタートアップと組むと学びが多い」という穏健派まで、その温度感はさまざまですが、日系企業ではスタートアップと組むのが正義とされている印象を受けます。
というのも、成功するスタートアップは、超絶技術を持っているという認識や、実績も知名度も資源もないのに、スピーディーに仕事をやっつけるというイメージがあるからかもしれません。
さらに、外国駐在で外から本社を見ると、大企業には実績が山ほどあって、誰もが知る看板があるけれど、何かと歩みが遅い…そんなフラストレーションを感じてらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
私自身の起業家やベンチャー投資の経験から見ても、スタートアップと「組む」こと自体をゴールにしない方がいいのではないかと思います。あるいは、やみくもにスタートアップを神聖視したり、やり方をマネするのもナンセンスです。
スタートアップとは新しい課題に対する新しい解決策を提案している新しい会社です。 そんなチャレンジをしているスタートアップのあり方や姿勢、つまり、イノベーションを共通の目的とするスタートアップから学ぶことを心掛けてみては?と思うのです。そんなスタートアップ文化を象徴する「ハック」と「ピッチ」という2つの技をご紹介しましょう。